大阪で揚重を依頼するなら、荷物や周囲の安全をしっかり確保する業者選びが重要となります。安全確認をするうえで重要になってくるのが、玉掛け作業における「3・3・3運動」と搬入する荷物の素材に合わせたスリング選びです。こちらでは、玉掛け作業のポイントやスリング選びの重要性などについてご紹介いたします。
玉掛け作業のポイントについて

厚生労働省では玉掛け作業において3・3・3運動を実施するよう定めています。いずれも荷物を安全に運ぶために必要なチェックポイントです。揚重のために玉掛けをする際には徹底して行わなければなりません。
地切り30cm
玉掛けをして実際にクレーンで対象を運搬する際は、30cmの位置で一旦停止する必要があります。一度に荷物を高く上げてしまうことで荷物が大きく崩れてしまったり、見落としていた不具合のせいで荷物が落下したりした際に、被害を最小限に抑えることが可能です。玉掛けが終わって荷物を吊り上げる際はまず30cmだけ上昇させます。これが地切り30cmです。
停止3秒以上
地切り30cm以上を実施したら、そのままの状態で3秒停止します。地上から30cmの位置で3秒以上保ち、ここで玉掛けが安全に実施できているのかをチェックするのです。もし玉掛けに不備がある状態なら、一気に上げてしまうことで荷物が周囲に散乱したり、場合によっては重量のある荷物で周囲の人が怪我をしたりする可能性も考えられます。そのため、3秒以上停止して安全確認をする必要があるのです。
3m以上離れる
玉掛けをした後に巻き上げると荷物が揺れるため、必ず3m以上離れるようにしましょう。その際、玉掛けワイヤーを張った状態で介錯ロープを持ち、荷物とワイヤーを再確認します。3m以内に人がいると接触してしまったり、挟まれてしまったりするリスクがあります。周囲の安全確保をするうえでも、玉掛け後に3m以上離れることが重要です。
玉掛け作業に使うスリングの選び方とは?

荷物の運搬では玉掛けの安全確認と同じくらい、スリング選びも重要です。実際に運搬する荷物の材質や重さ、重心などによっても使うスリングは変わります。主に「ワイヤーロープ」「繊維スリング」「チェーンスリング」が使われます。
ワイヤーロープ
玉掛け作業で目にする機会の多いスタンダードなスリングです。銅鉄線の頑丈なワイヤーなので強度も高く、長さや太さも豊富です。しかし、ロープの掛け方によってはロープ自体に癖がついたり、材質の関係でサビに弱かったりするデメリットもあります。そのため、形状の変化で切れやすくなっていないか、サビで劣化していないか、必ずチェックしてから使用しましょう。
繊維スリング
ナイロン繊維を主に使用しており、「スリングベルト」とも呼ばれています。柔らかく軽量で、扱いやすいのが特徴です。繊維素材は資材に傷をつけにくいので、荷物に傷をつけたりしないようにするのに便利なスリングです。ただし熱には弱いため、保管する際は直射日光を当てないよう冷暗所で保管するといった注意点もあります。また、摩耗や劣化が早いので使用前に荷物をしっかりと固定できるのか、強度のチェックも必ず行いましょう。
チェーンスリング
非常に頑丈で耐久性が強いという特徴を持っています。鎖状になっており、重量のある荷物を吊るしたり、耐久性を活かして何度も玉掛け作業をしたりするのに適しています。強度はあるもののチェーンスリング自体が重いので、何度も使用する場合は体力を消耗する点に注意が必要です。また、他のスリング同様、メンテナンスをしないとチェーンが切れてしまいますので日常的な点検が大切です。
揚重で重要なのは安全に玉掛けを行い、荷物に対して適切なスリングを使用することです。運搬する荷物はルールを守って玉掛けを実施することで、より安全に搬入が可能となります。こうした丁寧な荷物の運び入れは、現場での豊富な経験や資格を持ったプロに依頼することをおすすめします。
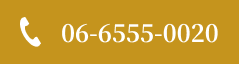
 ホーム
ホーム