神戸で荷揚げの依頼を検討する中で、どのような流れで作業が行われるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。作業の流れを知っておくことで、依頼もスムーズに進みます。こちらでは、荷揚げの流れと内装資材を搬入するときのコツについてご紹介いたします。
荷揚げの流れとは?
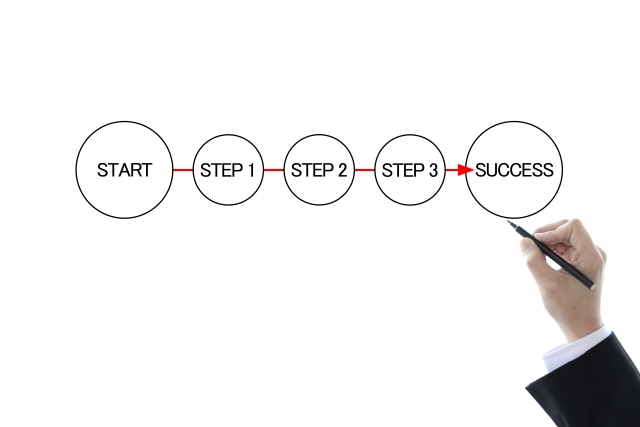
作業の流れ
複数の人員を運搬場所から目的の場所まで配置し、資材を流れ作業で運びます。目的の場所までの距離が近ければさほど人員はいらないものの、内装資材だと建物の4階以上に運ばなければならないこともあります。そのため、現場の担当者はどうすればスムーズに運搬が行えるか、十分に考慮する必要があります。よく考えて人員を配置することで資材を傷つけたり、スタッフが怪我をしたりすることなく資材を運べます。また、クライアントとのトラブルになるリスクを軽減することにもつながります。
高さのある建物での作業
3階以上の建物に資材を運ぶ場合は、階段だけでなくエレベーターも使用します。ただし、資材の大きさによってはエレベーターでの搬入が難しいです。その場合は階段を使って資材を運びます。2階部分への運搬なら、建物の外から外廊下やベランダ、バルコニー越しに資材を引き渡すこともあります。階段での運搬はスタッフの体力を消費するため、ここでも適切な判断が求められます。
クレーンやフォークリフトが入れない場所
内装資材などは1枚10キロ以上になるものもあるため、「クレーンやフォークリフトなどの重機を使用するとよいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。重機が入れる場所なら使用することで作業もスムーズに進みます。しかし、建物によっては重機が入り込めない場所もあります。その場合は人の手で資材を運ぶため、体力・腕力などに自信のあるスタッフを配置することになります。
内装資材の搬入のコツについて

内装資材は1枚につき10キロ以上と非常に重量があります。重たいものを適当に持っていては腰などを痛めてしまうため、何らかの対策を講じることが重要です。
荷物を持ち上げるときの姿勢
腕力に自信があっても、重たいものを力任せに持ち上げると腰を痛めてしまいます。腰を曲げた状態で資材を持ち上げるのではなく、中腰になってから資材に手を添えるようにしましょう。資材を手に持ったら、目線は前にして腰と膝の力で立ち上がります。腰を曲げてから持ち上げると腰に多大な負担がかかります。その点、中腰で持ち上げることで全身に負荷がかかり、腰痛を防止できるのです。
最初に腰や腕を痛めるとその後の作業にも影響が出るため、無理なく持ち上げる姿勢を意識しましょう。
資材は横持ちにする
内装資材は縦幅の長いものが多く、どこを持てばいいのかがわかりづらいです。持ち方を間違えると全身に負荷がかかって体力を消費するため、持ち方にも工夫が必要です。おすすめなのは内装資材を横持ちすることです。横向きにして資材の下に両手を添え、その状態で持ち上げてから運搬します。この方法なら素早く移動できるため、あまり時間をかけられない現場で活用可能です。ただし、腰に痛みを感じたら持ち方を変えるようにしましょう。
資材表面をくっつけて2枚で運ぶ
資材の表面をくっつけて運ぶこともコツの一つです。資材の表面に傷がつくと、その資材は使用不可となり施工ができません。また、賠償責任などが生じる可能性も考えられます。表面同士をくっつけることで傷がつくリスクを軽減できます。さらに、同時に2枚を運べるので作業時間も短縮しやすいです。ただし、1人で2枚を運ぶと落とす危険性があるため、無理せず2人以上で運ぶことも大切です。荷揚げ作業では作業員の疲れだけでなく、資材の傷にも注意しましょう。
荷揚げは作業前に人員配置などをしっかり考えたうえで行われます。資材に傷をつけることなく、スムーズな運搬が求められるため、実績のある会社に依頼することをおすすめします。
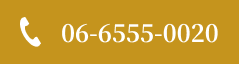
 ホーム
ホーム